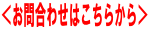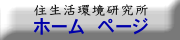構法のねらいと特徴

構法開発の想いとねらい。
NSU現代民家型構法は「住まい手」にとってどんな意味を持つのか
- これからの時代に求められる多様な「くらし方」に標準化で応えていく。
- 標準化されたユニット架構(不変部分)をベースにして多様な住宅ニーズに
柔軟(可変)に応えながら住まいとしての必要な構成要素を確保する。 - ユニット内には構造上必要な柱や壁がないため暮らしの変化にも
容易にリニュアールが可能。 - 長寿命な木組み架構と安心できる耐震性能。
- 標準化されたユニット架構(不変部分)をベースにして多様な住宅ニーズに
- 室内に構造材が表しになっている事が利点となる。
- 構造面でのメンテナンスがやりやすい。
- 木肌が表れていることで 心地よい室内空間となる。
- 木材が 夏の“調湿機能”冬の“保温機能”として働き
心地よい室内温熱環境になる。 - 自然材使用による安全で健康な室内空気質環境になる。
- 住み手を「中心」にした家づくり。
- 我が家の構造方式が理解しやすく その後の維持管理もやりやすくなる。
- 将来の増築・減築がユニット単位で行え「育てる家」「変化できる家」とすることができる。
- 統一感のある外部デザインにしやすくなり 地域になじむ居心地が良く
調和のとれた景観づくりができる。
森側(山側)はどんな利点があるのか
- 構造材の「単材供給」から「スケルトンユニット供給」へ
- 森とまちを直接むすび 地域材供給を円滑にさせるために ユニット構法として
「架構の標準化」を図ったことで 構造材が一本単位の供給でなく 「ユニット単位」
とすることで まとまりのある供給ができて 地域材が使いやすくなる。
- 森とまちを直接むすび 地域材供給を円滑にさせるために ユニット構法として
- 木部材と架構と規定化することにより 森側の製材などの生産性を高めることを可能にする。
- 木材の長さを「5m」で標準化しており 従来の定尺(長さ)の4mも 5mも同じ採材・製材の作業量のため
木材一本当たりの材積量が多いほど生産効率を上げることができる。
- 木材の長さを「5m」で標準化しており 従来の定尺(長さ)の4mも 5mも同じ採材・製材の作業量のため
- 製材寸法の標準化で 同じ寸法の梁材の転用使いを可能にする。
- 材の等級・品質により使い分けができる 適所適材の木材使用ができる。
- 材の等級・品質により使い分けができる 適所適材の木材使用ができる。
- 「標準化」により 製材木材のストックを可能とする
- 従来のような注文採材・注文製材から 計画的な採材・製材への切り替えが可能となる。
- ストック期間を利用した「自然(天然)乾燥」を可能にし 人工乾燥のための熱エネルギーをムダに消費しない。
- 人工乾燥による木材の「内部われ」や「変質」を避けることができる。
構法の特徴
なぜ梁勝ち・渡り腮による交叉梁組を採用した構法とするのか。
- 地震や強風などの水平荷重(横からかかる力)を壁に伝える床構面の確保。
- 建物を構造的に強くさせるには 壁面のみをいくら強くしても不十分です。
床面も強くして 水平荷重を確実に壁に伝える働きをさせて
建物のねじれにも耐えられる強さにする必要があります。 - ダンボール箱の蓋が開いたままですと いくらダンボールに厚さがあり丈夫でも
横から曲げるとねじれてしまいますが
上の蓋を閉じて箱状にするとしっかりして ねじれることもありません。
建物もこれと同なじで 床面が ダンボール箱の蓋の役割をするのです。 - さらに 建物の強さは「ただ強く耐える」だけではだめで
地震のように何度か繰り返される力に対して「粘って耐える」強さも必要であり
床構面に「粘り」を持たすために「渡り腮・交叉梁組」を採用しました。
NSU現代民家型構法はこの「床構面」の重要性に着目した構法です。
- 建物を構造的に強くさせるには 壁面のみをいくら強くしても不十分です。

- ねばりを持つ床構面にする方法として 渡りあごの「木のめりこみ抵抗」を利用。
- 右の写真を見てください
渡りあごは梁が交差している部分を少しずつ切り欠きしてかみ合わせています。
このかみ合わせ部が 地震などで建物がねじれたとき 同じようにねじれますが
そのときにかみ合い部分の木がめり込み合い ねじれに粘りながら抵抗する力が生まれます。 この力を利用した構法です。 - 「あいちの木需要拡大協議会」では あいち県産杉材のめり込み抵抗値を知るために 名古屋大学大学院生命農学研究科の佐々木先生と協同して「水平加力実験」を実施しています。
実験の結果 渡りあごの仕口1ケ所当たりのめり込み抵抗は「床倍率」にすると 0.24~0.29となることがわかりました。
これは火打梁に相当する床倍率であり、渡りあごと杉の厚板を組合わせることにより 強よさと粘りのある「床構面」を構成することができます。
- 右の写真を見てください
- 垂直荷重(上から架かる重さ)を受ける床面の構造方法を交叉梁組にすることでより
梁材のサイズダウンが可能。- 交叉梁組とすることで、垂直荷重を四方に分散できるため 梁のサイズが小さくなる。
- 連続梁構成となり、一般的な単純梁構成より梁のサイズが小さくなる。
- 小さいサイズの梁を使えるため 構造材のコストダウンが可能となる。
- 含水率が高い杉材の特性を考慮した「積み上げ架構方式」による木組みを採用。
- 梁を積み上げて組んでいく架構方式のため 一般的な架構方式で使われている
梁の横に溝を掘り別の梁をつなげる方式とは違い 木材の乾燥縮みによる
不具合が少ない組み方となります。 - また地震時も梁と梁が外れることもない組み方です。
- 梁を積み上げて組んでいく架構方式のため 一般的な架構方式で使われている
- 「標準ユニット化」とすることで 施工精度の向上と施工効率が向上します。
- 単純な仕口加工(渡りあご)の繰返しのため施工精度が良くなる。
- 同じ組上げ手順の繰り返しにより熟練度が高まる。
- 伝統構法的な「木組み構法」を特別な職人しかできないものとしないで
「普通の家」の建築構法にできる。 - 通し柱を使わない 梁勝ち管柱仕様にすることで 大型重機を使えない
狭小敷地の「建て方(棟上げ)」に有利になります。
- 「地域型住宅」として木造建築技術の継承に貢献できます。
- 現代では伝統的な仕口・継手加工ができる大工職人が少なくなってきていますが
この架構システムで 「伝承構法」として木造建築技術を継承していける。 - 地域の工務店や地場の大工さんによる「地域型住宅」の建築システムとして普及できる。
- 現代では伝統的な仕口・継手加工ができる大工職人が少なくなってきていますが