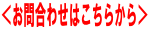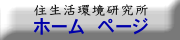スケルトン仕様


今までは日本の住宅の建替え年数は平均25〜30年といわれています。
住宅の寿命として これではあまりにも短かすぎます。
これからの住宅は社会的資産として「ストック」ができる
「長持ちする住宅」として建てるべきです。
そのためにはしっかりした構造矩体(スケルトン)と
長く住み続けるられるために 住まい手の暮らし方の変化にも
柔軟に対応できる 内装や設備(インフィル)にして
リフォームやリニューアルなどの「住まいの更新」が
やりやすい建て方にすることが大切です。
スケルトンの標準仕様
長く住み続ける住まいとして 変わることのない 変えてはいけない「仕様と性能」を
事前に定めて 選択の巾を持たせながらも「標準化」や「規格化」をして
家づくりの「ルール」をつくりました。
主なスケルトン仕様
- スタンダード化された「住宅構造仕様」。
- NSU 現代民家型構法
- 安心して暮す住まいに必要な建物性能として。
- 梁勝ち・渡り腮交叉梁組架構方法。
- 耐震性能。
- 建築基準法レベルの1.25倍以上の耐震性。
- 耐風性能
- 建築基準法レベルの1.25倍以上の耐風性。
- 劣化対策性能。
- 基礎スラブによる床下防湿処理。
- 床下点検のために床下空間350mm以上を確保。
- 土台 桧 4寸角。
- 管柱 杉 4寸角。
- 透湿性の高い耐震面材と通気工法で壁内結露を防ぐ。
など
- 快適に暮す住まいに必要な居住性能・外部環境性能として。
- 地域特性に見合った自然エネルギーの活用。
(プランニング時に 自立循環型住宅の設計手法を積極採用)- 自然風利用。
- 昼光利用。
- 日射熱利用。
- 日射遮蔽手法。
- 省エネルギー性能。
- 熱損失係数「Q値」: 3.3 ~2.7 kw/㎡k。程度(省エネ対策等級 3~4 相当レベル)

- 熱損失係数「Q値」: 3.3 ~2.7 kw/㎡k。程度(省エネ対策等級 3~4 相当レベル)
- 使用断熱材。
- 木質系の自然素材断熱材。(断熱材の蓄熱容量を考慮して選定)
グラスウールは使いません。 - 壁の断熱材厚さは次世代省エネ基準 相当レベル。
- 屋根については夏の熱対策を重視した遮熱工法。
- 木質系の自然素材断熱材。(断熱材の蓄熱容量を考慮して選定)
- 外壁防火性能。
- 防火構造仕様。
準耐火構造仕様にすることも可能。
- 防火構造仕様。
- 外壁遮音性能。
- 遮音性能の高いボードを外部に使用して
外部騒音や生活騒音の漏れを軽減させる。
- 遮音性能の高いボードを外部に使用して
- 地域特性に見合った自然エネルギーの活用。
- 「長期優良住宅」対応について。
- 「木造スケルトンの家」は 独自構法と 構造用合板を使わず ムク木材の採用を優先したり
構法特性や地域性に見合った省エネ方法としているため
標準仕様のままでは 一部「長期優良住宅」の認定基準を満たさないところがあります。
長期優良住宅の認定基準とする場合は 標準仕様を一部変更することで「長期優良住宅」仕様にすることはできます。
- 「木造スケルトンの家」は 独自構法と 構造用合板を使わず ムク木材の採用を優先したり
外観デザインに関わる外装部の仕様
標準化されている仕様から選択して 組合わせしながらデザインしていきます。

- 主な標準仕上げ材
- 屋根材
- ガルバニュウム鋼板
- 陶器平瓦
- 外壁材
- 杉板張+自然塗料塗り
(板の張り方でデザインが変化します) - ガルバニュウム鋼板
(鋼板の折り方でデザインが変化します) - モルタル下地+左官塗り壁
(塗り壁の種類と塗り方でデザインが変化します)
- 杉板張+自然塗料塗り
- 外部建具
- アルミサッシ(防火地区指定のある地域内)
- 防火地区指定がない地域の場合は
ご要望により木製サッシとすることもできます。
- 屋根材
インフィルの仕様
住み手のくらし方はさまざまです。
このくらし方に合わせて居住空間と居住環境をオーダーにより「個別対応」していきます。
居住空間づくり

- 室内プランニング。
- 生活の中心となる「間」の検討。
- 家事・水回りスペースのつながり検討。
- 間仕切位置・間仕切方法。
- 内装仕上材の選定。
- 建具デザイン。
- 造り付け家具の選択。 など
居住環境づくり
- 室内の空気質環境性の程度設定。
- アレルギー対応の必要性と程度。
- 室内化学物質放散量低減対応の必要性と程度。
- 室内の温熱環境性の程度設定。
- 夏場の日射遮蔽と調湿対応性の必要性と程度。
- 冬場の日射取得と蓄熱性の必要性と程度。
- 床暖房採用の有無。
設備環境づくり
- 住宅設備プランニング
- 生活に必要な設備内容の計画
- 設備維持管理対策の計画
- 環境設備プランニング
- 太陽熱利用・太陽光発電などの環境機器採用の有無検討
- 省エネ設備機器の採用程度の検討